This video was published on 2018-04-07 06:47:05 GMT by @imogarabokuto1250 on Youtube.
imogarabokuto1250 has total 59.6K subscribers on
Youtube and has a total of 1.2K video.This video has received 0
Likes which are lower than the average likes that imogarabokuto1250 gets . @imogarabokuto1250 receives an average views of 1.4K
per video on Youtube.This video has received 0
comments which are lower than the average comments that imogarabokuto1250 gets .
Overall the views for this video was lower than the average for the profile.


















































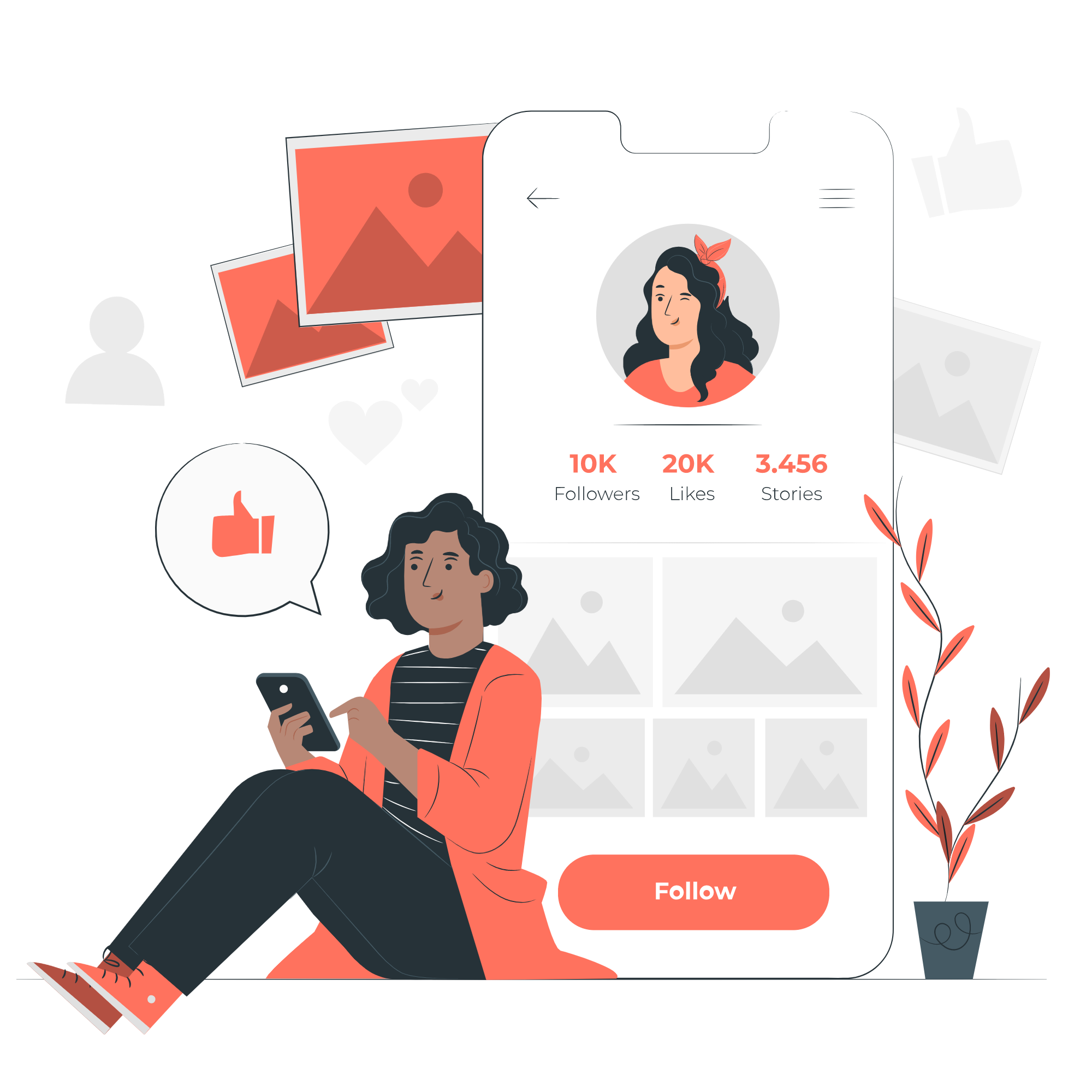



imogarabokuto1250's video: 2
0
0